富山地方鉄道(富山地鉄)が、本線の滑川〜新魚津間について、沿線自治体の支援がなければ早ければ2026年11月末にも廃線とする方針を打ち出しました。
地域の通学や生活の足を担うこの区間が消えると、住民生活や地域の魅力にも大きな影響が及びます。
当記事では、滑川〜新魚津間の現状、通学事情、経営課題、今後の選択肢などについて考察します。
廃線問題の背景
滑川〜新魚津間は、あいの風とやま鉄道とほぼ並行するルートをとっており、乗客が分散することで富山地鉄の収益悪化につながっています。
駅の設置数が多く、地域密着型である一方、浜加積(47人)、早月加積(35人)、越中中村(8人)、西魚津(115人)など、1日あたりの乗降客数は非常に少なく、鉄道本来の大量輸送の強みを活かせていないのが実情です。
経営面では富山地鉄全体で年間約7億円の赤字、累積赤字は61億円に上っており、持続可能な運営が困難な状況にあります。
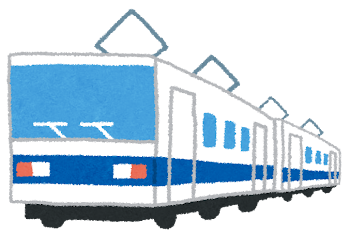
通学の現実
滑川高校の最寄り駅・西滑川駅は、多くの生徒にとって通学の要です。
学校によれば、生徒の約3割が地鉄を利用しており、南の上市町や舟橋村、立山町、東の魚津市や黒部市などから通学する生徒が多数います。
廃線となれば、「魚津駅から滑川駅まで歩くしかない」「通学が遠くなる」といった声も上がっており、生活の質が大きく損なわれる恐れがあります。
地域交通の意義
地鉄は単なる移動手段ではなく、地域の魅力や活力を維持する基盤でもあります。
元富山市長・森雅志氏は「公共交通が都市の人格、いわば“都市格”を高める」と指摘し、単なる赤字補填ではなく、市民生活の質を向上させるための投資と位置づけるべきだと訴えています。
特に地方都市では、公共交通の衰退が企業誘致や人口維持にも直結する深刻な問題です。
新たな経営形態
累積赤字が公費投入への障壁となっている中、森前市長は「新会社を設立し、そこに運行を委託する」案を提案しています。
新会社は累積赤字を引き継がず、資本金のみでスタートするため、公費を投入しやすくなり、透明性も確保されます。
運営の持続性を保つ上で、過去のしがらみにとらわれない仕組みづくりが求められます。
ネット上での反応と声
ネット上では、
・「地鉄がなくなると通学に支障が出る」
・「地域から公共交通がなくなるのは寂しい」
といった不安の声が広がっています。
一方で、
・「新しい経営体制で再生してほしい」
・「行政と協力して持続可能な形にしてほしい」
といった前向きな意見も見られ、地域交通の価値を再認識する契機ともなっています。

まとめ
富山地方鉄道・滑川〜新魚津間の廃線問題は、単なる経営の問題にとどまりません。
通学や生活の足として、そして地域の「都市格」を形づくる要素として、公共交通の価値を見つめ直す時期にきています。
行政・企業・市民が一体となり、持続可能な交通インフラをどう守り、どう再構築するかが問われています。
当記事は以上となります。
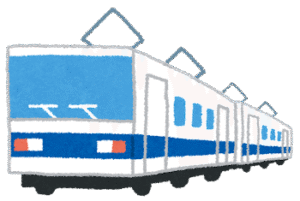


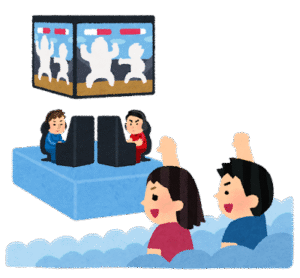





コメント