第172回直木賞に選出された伊与原新さんの短編集「藍を継ぐ海」は、日本各地の自然・文化・科学を背景に、人々の「継ぐ」物語を丁寧に描いた秀作です。
地球惑星科学の知見を活かしつつ、心に響く人間ドラマを紡ぐ理系作家の新境地とも言える本書。
当記事では、その魅力や反響などについて深掘りします。
「藍を継ぐ海」の魅力
本書は5つの短篇で構成されており、徳島、奈良、長崎、北海道、山口を舞台に、科学・自然・伝統と深く結びついた人間ドラマが展開します。
地理や生態、歴史に基づくストーリーは幅広い知見を提供しつつも、読者が没入できる感情の機微を大切に描かれています。
特に表題作「藍を継ぐ海」では、ウミガメの産卵・回帰の科学に触れながら、中学生の沙月とウミガメ監視員の佐和、カナダから来たティムとの関係が、命と未来への希望を交錯させます。
読後には目が熱くなるような余韻を残します。
また、「星隕つ駅逓」では北海道遠軽で拾われた隕石を巡る物語から、戦後の郵便制度やアイヌの歴史も横断しながら、丁寧に真実へ迫ります。
引用:株式会社新潮社
著者・伊与原新さんとは
伊与原新さんは1972年大阪生まれ。神戸大学理学部、東京大学大学院で地球惑星科学を専攻し、博士課程まで修了された理系作家です。
2010年に「お台場アイランドベイビー」で横溝正史ミステリ大賞を受賞。
2019年には「月まで三キロ」で新田次郎文学賞など複数受賞歴があります。
科学的視点で世界を描きつつ、そこには必ず人間の葛藤や温かさが含まれており、「藍を継ぐ海」でもその特徴が発揮されています。
引用:株式会社新潮社
ネット上での反応とレビュー
ネット上では、下記のような声が寄せられてます。
・「科学を文学に絡めた読み応えがある」
・「科学の持つ力と人間らしさが見事なバランスで存在していた」
・「水深のような没入感。1つ1つが信じられないほど深い短篇」

まとめ
「藍を継ぐ海」は、第172回直木賞受賞にふさわしい、科学と人間の絆を紡ぐ短篇集です。
自然と向き合い、歴史や文化とつながる人々を登場させることで、「継承」と「未来」への希望を静かに描きます。
心に余白を与えるような読後感は、忙しい日常に彩りを添えてくれるはずです。
科学や自然、地方文学に興味のある方には、ぜひ手に取って読んでほしい1冊です。











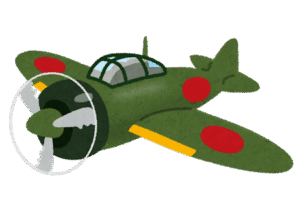
コメント